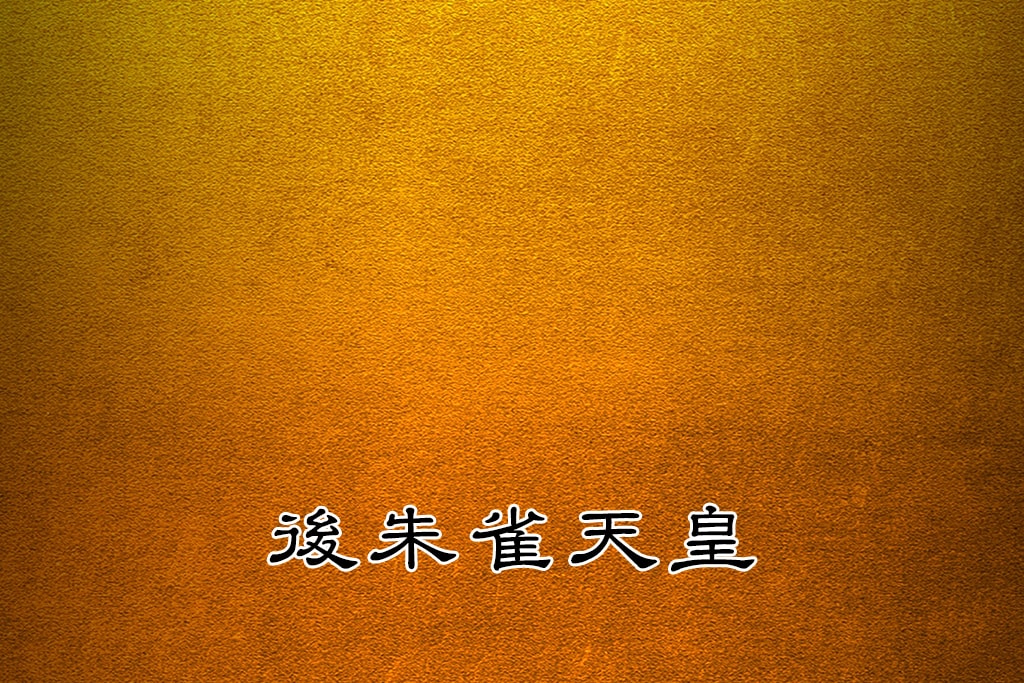第69代後朱雀天皇の時代は、藤原道長・頼道が政治を動かしたといっても過言ではありません。
ここでは第68代後一条天皇から第69代朱雀天皇時代に政治を動かした、藤原道長・頼道についてご紹介します。
後朱雀天皇即位の経緯
先帝である後一条天皇の即位に伴って、皇太子となった敦明親王が自ら皇太子を辞退したことによって、敦良親王(後の後朱雀天皇)は皇太子となりました。
後一条天皇には後継ぎとなる男子が産まれなかったので、弟である敦良親王が皇太子となったのです。
後朱雀天皇は闊達な性格で、兄である後一条天皇よりも厳格なところもあり、天皇としての職務を果たそうと努めていたと伝えられています。
しかしこのころの朝廷は、藤原道長の息子であり後朱雀天皇の叔父である関白頼通の影響力が大きな時代でした。
なので、なかなか後朱雀天皇は自分の意のままに政治を行えないことに苦悩していたとも伝えられています。
後朱雀天皇は政治的実績をほとんど残すことはできませんでしたが、和歌には優れていたと伝えられており、「後拾遺」「新古今」などの勅撰歌集に歌が残されています。
そして37歳で肩の悪性腫瘍により崩御、御陵は現在の京都市右京区にある円乗寺陵です。
藤原道長の息子である藤原頼通
平安時代に栄華を極めた藤原氏の象徴である、藤原道長の息子が藤原頼通で、先帝である後一条天皇の時代に道長から摂政を引き継ぎました。
藤原頼通も優秀な人物でしたが、父である道長の発言力が強く、様々な場面で板挟みになり、気の病(現代でいう鬱病のようなもの)になった時期もありました。
藤原頼通は、第66代一条天皇の時代にその時の天皇である一条天皇のいとこの隆姫という女性を正室として迎えました。
道長の威光が反映された政略結婚ではありましたが、頼通と隆姫は仲睦まじかったと伝えられています。
頼通と隆姫との間にはなかなか子が産まれなかったこともあり、天皇(その当時は三条天皇)から娘を降嫁をさせるという話が来ましたが、頼通は「妻が悲しむから」との理由で断ったとされています。
また、父である道長からも天皇からの降嫁をすすめられたにも拘らず、最後まで妃は隆姫だけでした。
頼通に子女が産まれなかったので、今までの藤原氏のように娘を天皇に嫁がせることができず、天皇家との深い絆を維持することができませんでした。
これが、その後の藤原氏の衰退の一つの原因だとされています。