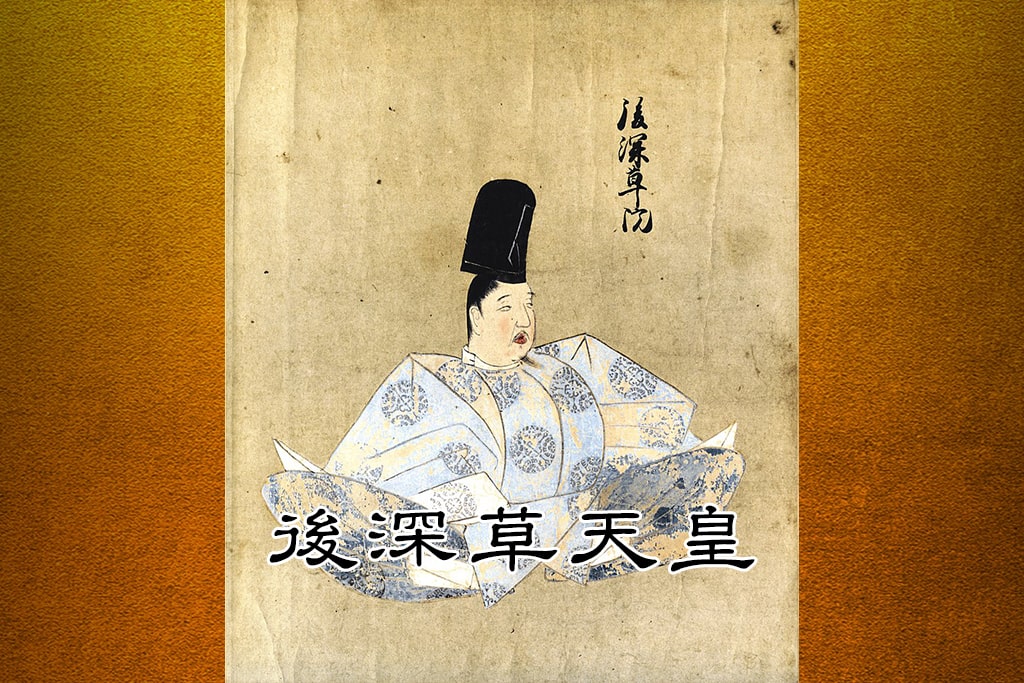鎌倉時代初期の承久の乱の後、朝廷が二つの系統に分かれるという事態が起こりました。
ここではそのきっかけの一人となった後深草天皇と、その前後の朝廷の事情をご紹介します。
後深草天皇、即位の事情
後嵯峨天皇の譲位によって第89代後深草天皇が誕生しました。
即位の時、後深草天皇は満2歳、父である後嵯峨上皇が院政を敷いて政治を執っていました。
後深草天皇は幼いころから体が弱かったといわれており、17歳のころに病に倒れたことで、後嵯峨天皇の要請で同母弟の亀山天皇に譲位することになりました。
この時代の天皇継承は本人の意思とは関係なく行われることが多かったのですが、後深草天皇の場合は、明らかに父である後嵯峨天皇が亀山天皇を寵愛していたからと考えられます。
そして亀山天皇の次の天皇は後深草天皇の子がなるのが通例だったのですが、亀山天皇の子が立太子してしまうのです。
立太子とは、天皇の後継ぎとして公認することです。
後深草天皇は上皇や幕府に訴えるのですが聞き入れてもらえず、結局第90代亀山天皇の後は、第91代後宇多天皇が即位することになりました。
その後、後深草上皇は朝廷内や幕府などに働きかけて自分の子である第92代伏見天皇に譲位させることに成功します。
伏見天皇の即位に伴い後深草天皇は上皇となり、朝廷内で権勢を発揮して、皇子である久明を鎌倉幕府の将軍に擁立することにも成功しました。
この伏見天皇が持明院殿に住んでいたので、この系統を持明院統と呼ぶようになったと伝えられています。
持明院統と大覚寺統の確執
この後草深天皇そして伏見天皇の系統を持明院統といい、対立する亀山天皇そして後宇多天皇の系統を大覚寺統といいます。
ここからしばらくの間、この二つの系統の争いが続き、結果的に朝廷の権威まで貶めてしまうのです。
承久の乱以降、天皇継承に関しては幕府に最終決定権がありました。
しかし、天皇の系統が二つに分裂して争うことは幕府の意向ではなく、むしろ幕府はお互いの仲介役に回っていたと伝えられています。
幕府は仲介に入った際に、持明院統と大覚寺統から交互に天皇を出すことで一応は一件落着しました。
その後、持明院統が北朝、大覚寺統が南朝となって南北朝が争う時代が室町時代まで続きます。
持明院統は、代々幕府に頼ることが多く幕府とは友好関係にありましたが、それに比べ大覚寺統は幕府とはあまり仲が良くなかったと伝えられています。