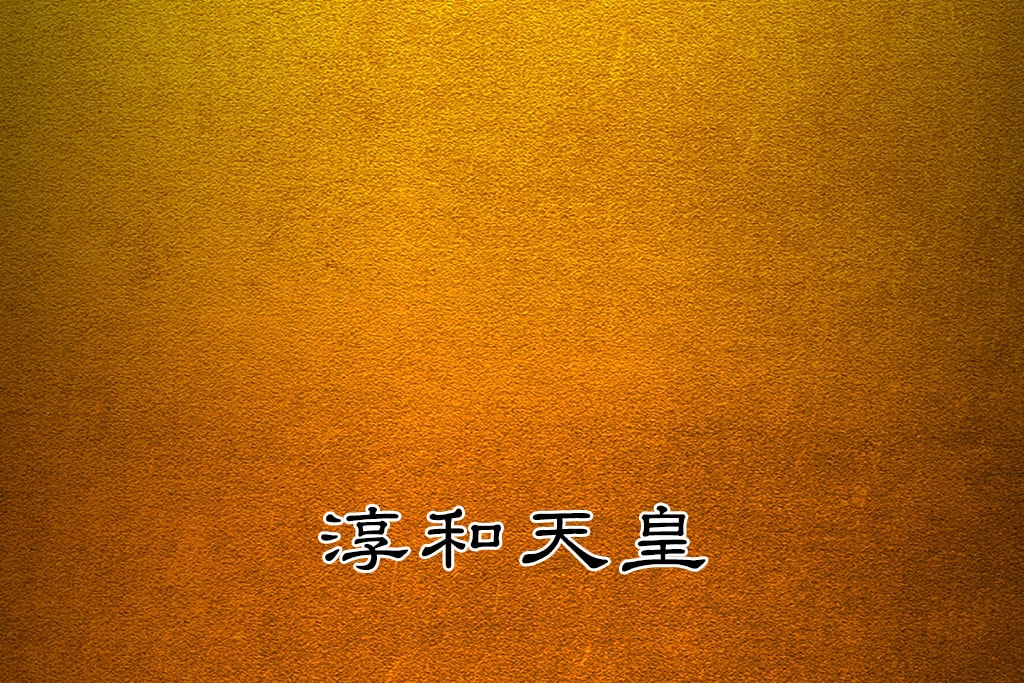第53代淳和天皇は別名西院帝とも呼ばれた、名君であった先帝第52代嵯峨天皇の異母弟です。
ここではその淳和天皇についてご紹介します。
淳和天皇即位と実績
兄である嵯峨天皇の時代、皇太子(時期天皇候補)にはもう一人の兄である高丘親王が定められていました。
ところが薬子の乱によって高丘親王は失脚し、嵯峨上皇に信頼されていた大伴親王(後の淳和天皇)が皇太子となり天皇に即位しました。
嵯峨上皇が愛娘を淳和天皇に嫁がせたことからもわかるように、嵯峨上皇は淳和天皇に厚い信頼を寄せていたのです。
絶対的権力を持つ嵯峨上皇の庇護のもと、しばらくは平和な時代が続いたのですが、嵯峨上皇が崩御すると皇位継承問題が勃発するのです。
淳和天皇は後院(上皇の御所)の淳和院が西院と呼ばれていたので西院帝とも呼ばれています。
淳和天皇は、清原夏野ら優秀な官吏の登用を積極的に行って、荒れた地方政治を正し、土地対策を行って税収の増加に努めました。
また、律令の解説書である「令義解」や「日本後紀」の編纂も行いました。
淳和天皇の最期
淳和天皇は最期まで、偉大なる兄である嵯峨天皇(嵯峨上皇)の影のように目立つことのない一生だったと伝えられています。
そして後継者に不安を残しつつ54歳の生涯を終える臨終の際に、自分の陵や葬儀は一切不要だと薄葬を望んだのです。
薄葬とは、従来の厚葬から、墳墓の規模や副葬品を簡略化させることを指し、先帝である嵯峨天皇も薄葬を遺詔したと伝えられています。
また中国の古事に倣って、殉死を廃し民衆や動物の犠牲を禁止し、陵造りにかける時間も大幅に短縮するものです。
そして淳和天皇は、自分の遺骨は山の上から撒くようにとの指示を出しましたが、帝王の散骨など過去に例がありませんでした。
困惑した廷臣たちでしたが、淳和天皇の意思が変わらなかったことで、遺骨を粉々にして平安京を見下ろす大原山の上から撒いたといわれています。
現在の散骨の走りと考えられます。
小塩山の淳和天皇陵
淳和天皇の遺言通り、遺骨は大原山の上から散骨され、御陵は造営されませんでした。
なので、おおよその散骨の場所は分かっていましたが、幕末までは淳和天皇の御陵はありませんでした。
しかし、幕末の尊王思想によって全ての天皇陵の造営および整備がなされ、淳和天皇陵もその際に新造されました。
この陵を大原野西嶺上陵といい、標高642mの小塩山の山頂にあります。
現在でも車道はなく、徒歩で山道の4㎞を登っていくという、数ある御陵の中でも参拝が難しい御陵といわれていますが、淳和天皇の遺志通り京都(平安京)が見渡せる風光明媚な場所です。