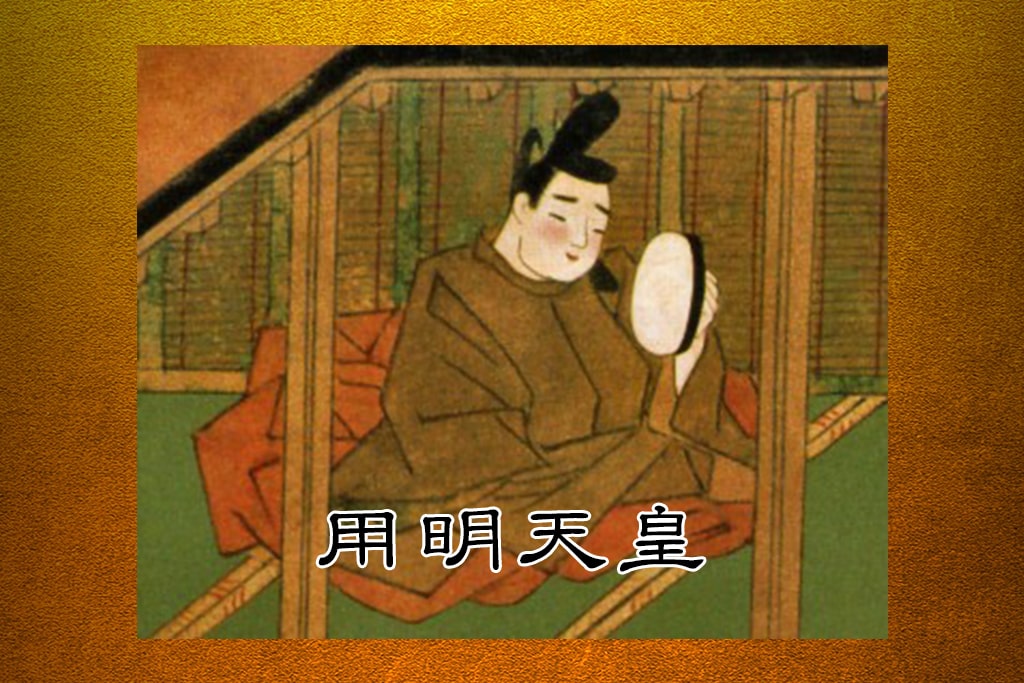第31代用明天皇の時代に起こった蘇我氏と物部氏の争いは、この後の歴史に大きく影響します。
ここでは用明天皇と、この時代の蘇我氏や物部氏ら豪族の動きについてご紹介します。
蘇我氏の血を引く用明天皇
第30代敏達天皇の没後、異母弟である用明天皇が即位しました。
用明天皇の母は蘇我稲目の娘である堅塩媛で、用明天皇は蘇我氏の血を引く初めての天皇です。
用明天皇は在位がわずか二年ほどと言われており、崩御の際に「三宝(仏・法・僧)に帰らむとおもう」と、初めて仏教の受容を自ら表明したと言われています。
崇仏派であり、蘇我氏を外戚に持つ天皇の登場は、これから先の蘇我氏の隆盛に繋がるきっかけになりました。
ちなみに用明天皇は、かの有名な聖徳太子(厩戸皇子)の父親です。
異母弟穴穂部皇子の天皇への野望
用明天皇の先帝である敏達天皇の葬儀の際に、蘇我馬子と物部守屋はあからさまに罵りあいをしていたという記録が残っています。
蘇我馬子と物部守屋は、ともに大和政権で大きな権力を持っていましたが、蘇我氏が仏教容認派だったのに対して物部氏は反対派でした。
そしてとうとう争いへ発展してしまうのです。
それは、用明天皇の異母弟である穴穂部皇子が皇位簒奪を目論んだところから始まりました。
敏達天皇の葬儀の際、穴穂部皇子は次の天皇が用明天皇と決まっていたにも関わらず、自分を皇位につけるように主張したのです。
しかし誰からも支持されず人々の不評を買うだけで終わりましたが、用明天皇の即位後に思わぬ行動に出ました。
先帝である敏達天皇の皇后である炊屋姫(のちの推古天皇)を関係を持って取り込もうとしましたが、敏達天皇の臣下である三輪逆に遮られました。
画策に失敗した穴穂部皇子は、物部守屋と蘇我馬子に協力を求めましたが、蘇我馬子はこの甥に自重を促しました。
ところが、物部守屋は穴穂部皇子の命に従って三輪逆を討ち、穴穂部皇子と結託してしまったのです。
物部氏の滅亡へ
即位に固執する穴穂部皇子を立てる物部氏と、それを阻止したい蘇我氏との対立が決定的になりました。
そして用明天皇の没後、ついに丁未の乱といわれる武力衝突へ発展していきました。
初めに物部守屋が狩猟を目的に軍を動かしましたが、その策略を見抜いた蘇我馬子は炊屋姫(のちの推古天皇)の詔を奉じて穴穂部皇子を討たせました。
そして蘇我馬子は、その勢いを駆って物部守屋追討軍を編成します。
結果、ほとんどの皇族や豪族が物部守屋追討軍に参加し、その中には用明天皇の子である聖徳太子(厩戸皇子)もいたということです。
これによって物部守屋は討ち取られ、物部氏は滅亡への道をたどるのです。