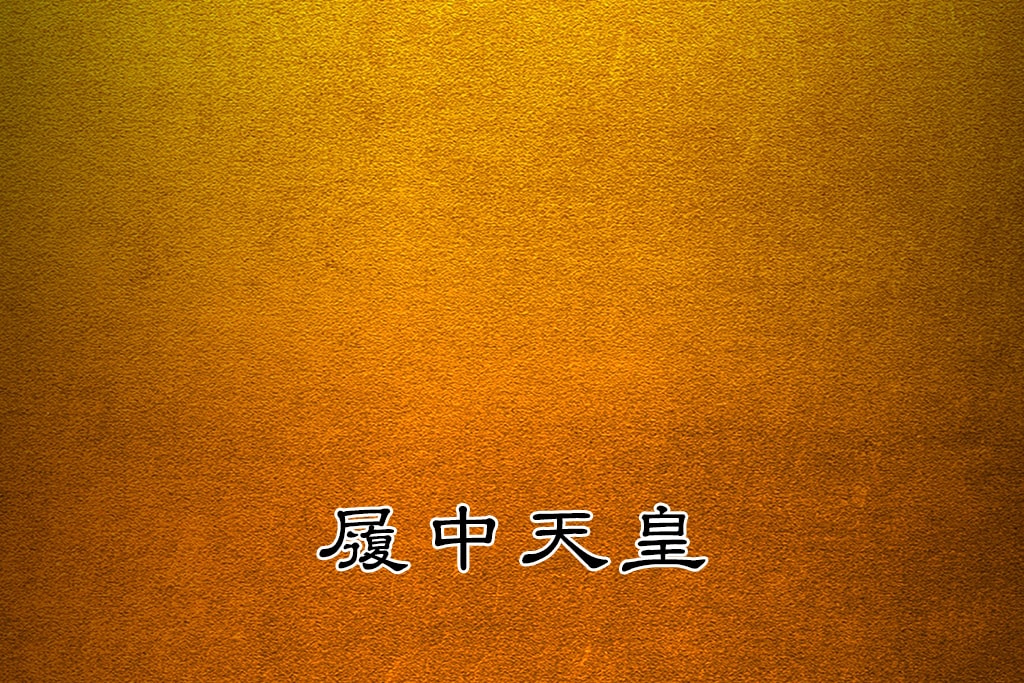第17代履中天皇は、聖帝と呼ばれた仁徳天皇の長子です。
履中天皇即位の際の動乱と、その際に逃げ込んだ石上神宮についてご紹介します。
履中天皇即位の動乱
先帝である仁徳天皇は聖と呼ばれ、善政を行い民衆からも慕われ、安定した時代が続きました。
ところが、仁徳天皇が崩御した直後に暗雲がたちこめるのです。
仁徳天皇のあとを継いだのはその長子である履中天皇ですが、仁徳天皇が崩御してすぐに、履中天皇の実弟である住吉仲皇子が履中天皇を襲撃しました。
その原因は、履中天皇と住吉仲皇子との間に起こった妃をめぐる争いと、日本書紀には記されています。
先帝の喪が明けると、履中天皇は美女と評判の高い黒媛という女性を妃に迎えようと、住吉仲皇子と使者として遣わせました。
ところが黒媛の美しさに心を惹かれた住吉仲皇子は、自分が皇太子であると偽って黒媛と深い関係になってしまいます。
そして黒媛の元に、自分がいつも携帯していた鈴を置き忘れてきたことで、一部始終を履中天皇に悟られてしまうのです。
兄の怒りを恐れた住吉仲皇子は先手を打って、履中天皇(このころはまだ即位前)のいる難波の宮殿を急襲し、火を放ちました。
履中天皇の難を聞いて、末弟の端歯別命が駆け付け住吉仲皇子の側近を使い討ち果たしたとされています。
この乱を鎮圧した端歯別命を、後に履中天皇は厚く遇しました。
履中天皇と石上神宮の関り
住吉仲皇子の乱の際に、履中天皇は難波宮から石上神社に逃げています。
その途中で少女に出会い、途中に伏兵がいるので遠回りすることを進められ、石上神社へ着いた際に以下の歌を詠みました。
「大坂に遇うや嬢子を道問へば 直には告らず 当岐麻路を告る」
直に行けば楽な道だったのですが、二倍の距離の困難な山道を越えて石上神社へ向かうことになりました。
近道は伏兵がいたために危険で、困難な山道の方が安全だったのです。
履中天皇は、この時酒を飲んで酩酊状態だったようで、部下に頼んでやっと馬に乗ることができたという逸話が残っています。
石上神宮はイシノカミジングウ、イソノカミジングウと読み、履中天皇の時代には石上振神宮という記述もされています。
現在の奈良件天理市にあり、祭神は布都御魂大神 となっています、ちなみに布都御魂大神 は皇室とは関係がないとされています。
石上神宮は拝殿が国宝にしてされており、現在でもたくさんの参拝者が訪れる有名な神社です。
国宝であり日本最古の銘文をもつ七支刀 (しちしとう) や、重要文化財である剣や勾玉なども収められています。